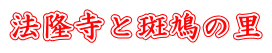
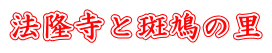
| 平成26年7月20日、奈良から大和路快速に乗車、法隆寺で下車して、炎天下の中、止めどなく流れ落ちる汗を腰のタオルで拭いながら、久しぶりに斑鳩の里を歩いてきた。「法隆寺と斑鳩の里」は、既に私のホームページ「花と鳥と古寺巡礼」で紹介しているので、ここでは写真を中心に掲載することとする。 |
このホームページの音声・画像・文章等の複製・転載は固く禁止します。
| 藤ノ木古墳 |
 |
| JR法隆寺駅北口から法隆寺を目指し歩き出してまもなく小雨が降ってきた。法隆寺参道の松並木の間の、少し湿った砂利道を踏んで南大門前へ。そのまま法隆寺を見学してもよかったが、今日は、藤ノ木古墳を見てやろうと、ここから西に折れて、古い街並みの西里を400m程歩いた。藤ノ木古墳に着いた時は、幸い雨は止み、すっかり晴れていた。 発見当初の騒ぎが嘘のように、藤ノ木古墳は、静寂の中にひっそりと佇んでいた。私は、傍らのベンチに座って、目の前の小さな古墳を眺めながら、被葬者といわれている穴穂部皇子と宅部皇子、あるいは崇峻天皇の、ともに蘇我馬子に非道にも暗殺された遙か古代の物語に思いを馳せた。無惨にうち捨てられた遺体を哀れと思った聖徳太子が、時の最高権力者蘇我馬子に遠慮しながらも、憐憫の情止み難く、この斑鳩の里に、王族としては誠に小さなこの塚を築いて埋葬し弔ったのであろうか。 |
| 法隆寺 |
| 西院伽藍 |
| 法隆寺(西院伽藍)には、寺の玄関である南大門のほかに、西大門、東大門、中門がある。パンフレットの「法隆寺境内図」で見るかぎり、「北大門」はない。このうち、西大門は、通常の見学ルートから外れているので、通ることは滅多にないが、法隆寺境内を東西に貫く大通りを西から東へ、かって盛んに論じられた法隆寺の再建論争に思いをいたし、また、焼失したという若草伽藍の跡を偲びながら幅広い石だたみをぶらり歩いてみるのも一興である。それにしても、西院伽藍と若草伽藍の間を画する、何故、こんなに幅の広い大路が必要だったのだろうか。万一、南側の塔頭や寺務所に火災が起きても、北側の金堂や五重塔に火の手が及ばないようにと配慮したもの、あるいは金堂壁画焼失の経験から、火災が起きた時に消防車の進入を容易にするため、比較的新しく整備されたものであろうか。いずれにしても、この東西を貫く大路は、防火上の事由により、企図されたものと思われる。 |
 |
| 南大門 |
 |
 |
| 西大門 | 東大門 |
 |
|
| 西大門から東大門を臨む | |
 |
|
| 中門 | |
| 古代寺院は、現代風にいえば全寮制の学問寺であった。西院伽藍の廻廊を挟んで東西に建立された僧侶の寮が東室と西室である。やがて僧侶が子院や塔頭に移り住むようになると、空室となったために、その一部が改造され仏堂化されるようになった。聖徳太子をご本尊として祀る聖霊院(東室)、聖徳太子の三経を講義する三経院(西室)がそれである。妻室は、主人の住む大房(東室)に対し、若い僧や従者の住まいである小子房。妻室の名は、後世の呼び名と云う。 |
 |
| 三経院・西室 | |
 |
|
| 聖霊院・東室 | |
 |
|
| 妻室 |
| 西円堂は、前掲の西室・三経院や西円堂は、一般の見学コースから外れているために、見落とす人が多いのではないか。東の夢殿と同じ、八角円堂である。写真右側、向拝の柱の間にかすかに写っている釣鐘が、有名な子規の俳句「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」に詠まれた鐘である(後述)。 |
 |
| 西円堂 |
| 塔は、仏舎利を納める建物で、金堂とともに寺院の中心で、神聖な場所である。法隆寺では、五重塔と金堂を廻廊で囲む(後述するように、現在、廻廊で結ばれている大講堂・経楼・鐘楼は、もともとは廻廊外に位置していた)。 法隆寺の五重塔は、どこから見ても美しいが、ここでは中門前、西円堂、廻廊西南入口、聖霊院前から撮影した五重塔の写真を紹介しよう。 |
 |
| 中門前からの五重塔 |
 |
| 西円堂からの五重塔 |
 |
| 廻廊西南角の入口からの五重塔 |
 |
| 聖霊院前からの五重塔 |
| 写真は、あの有名な子規の「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」の句碑である。「法隆寺の茶店に憩ひて」とある。その昔、法隆寺境内のこの鏡池の畔に茶店があった。すると、子規は、鄙びた斑鳩の里のどこかで、遠くから聞こえてくる法隆寺の鐘の音を聞いたのではなく、法隆寺境内のすぐ近くで聞いたことになる。 この鐘は、廻廊とつながった「鐘楼の鐘」ではなく、明治になって西円堂の東に作られた「時の鐘」の鐘の音である。「鐘楼の鐘」は、現在と変わりがないとすれば、夏安居(5月16日から8月15日)の期間、朝9時に撞かれる。従って、柿の実のなる秋には鐘は鳴らない。一方、「時の鐘」(明治22年設置)は、午前8時から午後4時まで、2時間おきに撞かれたという。子規が茶店で柿を喰ったのは、何時の鐘の時であったろうか。 |
 |
| 子規句碑 |
| 日本書紀によれば、法隆寺は670年に焼失したというから、今の法隆寺は、その後に再建されたものということになる(通説)。しかし、金堂に安置されている本尊の釈迦三尊像(光背銘に623年止利仏師作)にも薬師如来座像(光背銘によれば607年に用明天皇の意志を継いだ推古天皇と聖徳太子が造立)にも全く火災による損傷の痕がない。何百キロという重さの金銅仏を、火災のさなか無傷で運び出したとは到底思えない。また年輪年代法による調査によれば、金堂や五重塔の部材は、例えば五重塔の心柱の標本は594年に、また金堂の天井材は668年に伐採されたヒノキ材という。いずれも法隆寺が焼失した670年よりも古い。このことから、焼失した法隆寺(若草伽藍)が現存していた時から、既に建設されていたと主張されている。 以前と比べ、金堂内の照明がLED化され、随分と明るくなった。そのおかげで、懐中電灯で照らすことなく、仏像や壁画をはっきりと見ることが出来るようになった。 |
 |
| 金堂 |
| 東室・西室の僧房を僧が起居する寄宿寮とすれば、講堂は講義を受けたり、討論する大教室であった。堂内左右に論議台があるのは、そのためである。現在のお堂は、925年に落雷のより焼失した後の再建。 |
 |
| 大講堂 |
| 西院伽藍の金堂と五重塔をぐるっと取り巻く廻廊。現在、廻廊は経蔵・鐘楼・大講堂とつながっているが、大講堂が再建されるまでは、経蔵・鐘楼・大講堂は、廻廊の外にあった。 |
 |
| 廻廊 |
| 経楼は経文を収める建物であるが、現在は天文や地理学を日本に伝えたという百済の学僧・僧勒僧正と伝える坐像を安置している。鐘楼には白鳳時代の梵鐘が吊るされており、今も夏安居(夏の修業)の期間、毎日朝9時に、1300年の時を超え悠久の音色を斑鳩の里に響かせている(ただし、昔と変わらない美しい音色とはいえないようです)。 鐘楼の写真(下段右)に写っている青銅製の大灯籠は、徳川将軍綱吉の生母桂昌院が寄贈したものである。 |
|
 |
 |
| 経楼 | 鐘楼 |
| 綱封蔵は、寺宝を収納する高床の宝蔵、北倉・中の間・南蔵に分かれる。食堂は、日本最古の食堂と云われている。食堂に厨房があり、食堂と細殿で食事をしたのであろうか。詳しくは分からない。 | |
 |
 |
| 綱封蔵 | 細殿 |
 |
|
| 食堂 | |
| 平成10年の秋に、百済観音を収納するための百済観音堂を中心とする大宝蔵院が落成した。百済観音の他に、夢違観音(「ゆめちがい」と読むそうです)、玉虫厨子、金堂障壁画など多数の宝物を安置している。百済から来たという背の高い九頭身の百済観音像は、もともとからある法隆寺の仏像ではなく、どこかの寺から近世になって法隆寺に入った仏像らしいが、それ以上のことは、よく分からない。謎の多い仏像である。 |
 |
 |
| 大宝蔵院入口 | 百済観音堂 |
| 東院伽藍 |
| 八角堂の夢殿を中心とする東院伽藍は、738年頃、行信僧都が斑鳩宮の跡地に、聖徳太子を偲んで建立したもので、もともとは法隆寺とは別の寺院であった。本尊の救世観音像は、聖徳太子の等身大の似姿像と云われ、明治時代になって、岡倉天心とフェノロサが、この秘仏の白布を取るまで、人の目に曝されることが無かった。今も秘仏である。 聖徳太子等身大の像といえば、他に金堂の釈迦三尊像がある。救世観音像も、当初は金堂に安置されていたが、夢殿が建立されるの伴い、夢殿に移されたとの説もある。金堂に残る飛鳥時代の台座(今は鎌倉仏の阿弥陀如来像がのる)の跡が、救世観音像の接地面(径約70センチ)とぴったりと一致するため、かっては救世観音像がこの台座にのって金堂に安置されていたのではないかと推測する。 |
 |
| 夢殿 |
| 聖徳太子の生涯を描いた障子絵を納める。元々の絵伝は、明治11年に皇室に献上され、現在は東京国立博物館の所蔵。 | 聖徳太子が二歳の春に、合掌した掌中から出現したという仏舎利を安置する。 |
 |
 |
| 絵殿 | 舎利殿 |
| 中門を改造したものと云う。礼門の南側には寺の玄関である南門がある。夢殿は、南に礼門、北に絵殿・舎利殿を結んだ廻廊により囲まれている。 | 梵鐘には、「中宮寺」と陰刻されている。鐘楼の東、絵殿・舎利殿の北並びに伝法堂が立つ。伝法堂は、聖武天皇夫人橘古那可智の住宅を仏堂に改造したものである。 |
 |
 |
| 礼殿 | 鐘楼 |
| 中宮寺 |
| 本堂は、昭和43年5月に耐震大火の近代的な建物に改められた(下段の写真)。この本堂の中に、本尊の菩薩半跏像と天寿国曼荼羅繍帳が安置されている。中宮寺は、僧寺の法隆寺に対し、尼寺として聖徳太子の斑鳩宮を挟んで東側に建てられた。旧地は、現在の東方500メーターの県道奈良・大和郡山・斑鳩線を超えた向うに土壇として残っている。南に塔、北に金堂を配する四天王寺式伽藍であったらしい。 | |
 |
 |
 |
 |
| 法輪寺 |
| 法輪寺は、聖徳太子の御子山背大兄王が太子の病気平穏を願って建立されたと伝える。 斑鳩三塔の一つとして親しまれた法輪寺の三重塔は、昭和19年、落雷により惜しくも焼失した。作家の幸田文などの尽力もあり、再び、この斑鳩の里の空高く相輪が天を摩したのは、ようやく昭和50年のことであった。風のある日には、恰も天人が奏でる如き妙なる風鐸の音が斑鳩の里に響くという。是非、一度、聞いて見たいものである。 妙見堂は、北辰(北極星)が仏格化された妙見菩薩をお祀りする。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
| 三重塔 | 金堂(上)と妙見堂(下) |
| 法起寺 |
| 法起寺は、聖徳太子が606年に法華経を講じたという岡本宮を寺に改めたものと伝える。聖徳太子は、622年2月、その死に臨み、長子の山背大兄王に、この宮殿を改めて寺とすることを遺命したという。 当初の伽藍は、中門を入って、右に三重塔、左に金堂、中央正面奥に講堂があり、廻廊は中門左右から堂塔を囲み、講堂の左右に接続する様式の伽藍であったと推測されている。聖天堂は、1863年に建立された堂である。 三重塔は、706年に建立された、我が国最古の三重の塔として名高い。私は、法起寺を訪れた時は、今は石壇のみを残す鐘楼跡の前のベンチに座って、この均整のとれた美しい三重の塔を時間の許す限り眺めて過ごすことにしている。 |
|
 |
|
 |
 |
| 池のスイレン | 聖天堂 |
 |
 |
| 入口(西門) | 講堂 |